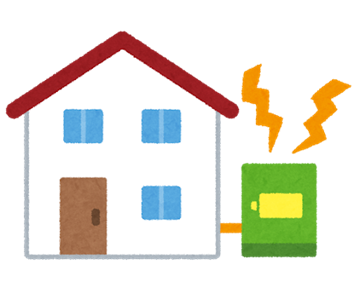
このところ、「不特法を活用して、蓄電池を対象としたファンドを組成したい」というご相談が増えてきました。
蓄電池ファンドは金融商品取引法が提供されるファンドではないのか?
でも、不特法で蓄電池ファンドを組成している例もあるような…??
そこで、本日は、「蓄電池ファンドを不特法(不動産特定共同事業法)で組成することができるか?」について解説します。
ファンド組成の可否
蓄電池ファンドを不特法(不動産特定共同事業法)で組成することができるかどうかは、対象となる土地が「宅地」に該当するかどうかにかかっています。
不特法の対象は、不動産から得られる収益や利益を分配する事業です。「不動産」とは、「宅地」または「建物」を指すため、蓄電池ファンドが不特法で組成できるかは、土地が宅地や建物を含むかどうかがポイントとなります。
1. 蓄電池収納施設と建物の関係
まず、重要な点として、蓄電池の収納施設が建築基準法上で「建物」には該当しないことが挙げられます。つまり、蓄電池の収納庫は「建物」とは見なされません。したがって、蓄電池ファンドを組成する際に、土地に「建物」があるかどうかが重要なポイントとなります。
参考:電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて (技術的助言)
2. 宅地かどうかの判断
次に、ファンドの対象土地が「宅地」に該当するかを判断する必要があります。宅地とは、以下のいずれかに該当する土地です。
<宅地とは>
・建物の敷地として利用される土地
・用途地域内の土地
用途地域内であれば問題なく宅地として認められるため、不特法ファンドの対象となります。
しかし、用途地域外の土地(無指定区域や非線引き区域など)では注意が必要です。この場合、蓄電池収納施設が建物ではないため、他に建物がない土地は宅地に該当しない可能性が高く、その場合は不特法ファンドの対象にはできません。
3.結論
用途地域内の土地は問題なく不特法ファンドの対象となります。用途地域外の場合でも、土地に他の建物があれば、または建物を建てる予定があれば、不特法ファンドを組成することができます。
【今日の短歌】
蓄電所 用途地域の外ならば 建物なしに 不特にならぬ
蓄電池ファンドを不特法で組成するためには、土地が「宅地」として認められるかを確認することが重要です。事前にしっかりと確認し、法的要件を満たす土地を選定することが成功への鍵です!
以上、参考となりましたでしょうか?
不動産ファンドの組成に関する質問やご相談は、どうぞくるみ事務所までお寄せください。
皆様の事業推進を全力でサポートいたします🤗
